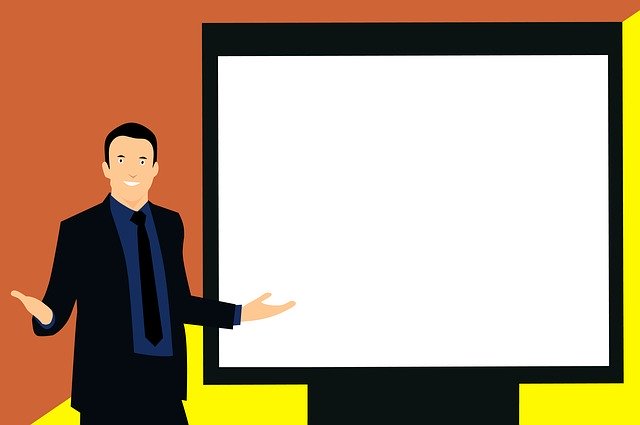
民間救急サービスを新たに始めるため、「患者等搬送乗務員講習」を受けてきました。
実際に学科授業を受けて学生時代の眠くなる授業を思い出したので、過去と現在で比較して思ったことをまとめてみようと思います。
書いてあることを読み上げるだけなら先生は要らないと思う
昔から自分は、テキストの読み上げだけなら印刷して配ってくれればいいのにと感じていました。
要点だけ押さえたものを印刷してくれれば、あとは個々人で勉強してくればいいですよね。
「ここテストに出るよ」は口頭で伝える必要ある?
事前に「テスト出るよ項目」をまとめて共有してくれれば、より要点を押さえやすいと思います。
本質としては、下記の3点でしょうか。
- 合格点を取ってもらうこと(短期)
- なぜその答えに行き着くのか思考してもらいたい(中期)
- どんな状況でも最適解を追求できるようになってほしい(長期)
そもそもテストという形式のほとんどは意味のない丸暗記だと思っているので、構造的に無理があるのかなとは感じます。
読み上げを聞いていると眠くなる
自分にとっての大きな障害は、いくら睡眠を取っていても先生の話が適度な睡眠を促してくれることです。
学生時代の私はそのまま意識を飛ばしていましたが、現在は「自分の得意な方向に思考していく」スタイルで覚醒できる事実に気が付きました。
本日の具体的な思考案は、今この講義を聞いていて私はどう思っているのか?という内容です。
大事な部分だけメモして、あとは学習している見た目とアウトプット・覚醒が同時に得られます。
仕組みを作る側に回ると問題点を回避するために工夫をしていける
すでに作られた仕組みを丸暗記するのと、自ら仕組みを作っていくのでは得られるものがまるで違います。
自らの損得につながる案件であれば、余計に集中して取り組めるでしょう。
ライター募集なんかは非常に考えさせられた
自身の経験ではライター募集を行った際、
- 自身の手伝いをしてほしい
- ジャンルと業務内容
- 報酬
- 注意点
上記を考えに考え抜いて募集文を作成しました。
いざ募集してみると誤解を生みやすかったり、指示不足だったりと読みの甘さが露呈しています。
とはいえそんな経験があるからこそ、なぜこの文言が大事なのか?押さえるべきポイントはどこか?を総合的に学べたのです。
勉強も丸暗記より仕組みづくりから学べないだろうか
すでに作られた仕組みを提示されても、なぜその仕組みを作るに至ったか背景がわかりづらいです。
学校も社会も「いいから手を動かせ」といったような、同じような仕組みで回っている感覚があります。
ただ説明をした段階で熱意を失う方は多いので、教えたり依頼したりする側もふるいにかける目的となりやすいなぁとも感じるのです。
学ぶ意欲や成長度が高い方を優先的に教えたほうが、効率は高いので仕方ないですよね。
まとめ:とにかく仕組みを作る側に回っていくのが大切だと思う
なにか作られたものに乗っかるより、自分で工夫したり作ったりするほうが楽しいと思うのです。
もちろんそう思わない方もいらっしゃると思いますが、自身の特性に気づけていない人も多いハズ。
明日は実技テストがあるのでAEDの使い方を復習してきます。

