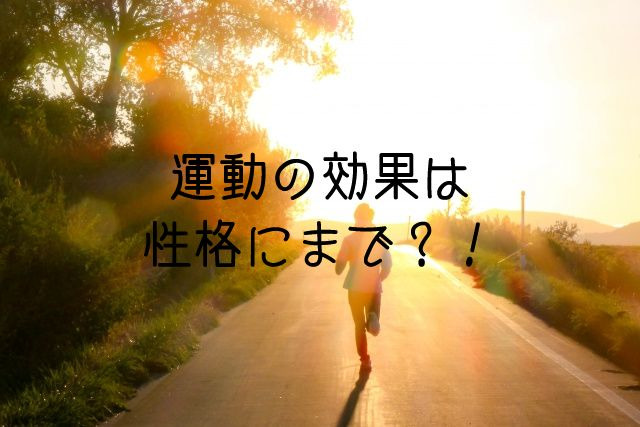
デスクワーカーから卒業して歩数が4000→1万2千歩に増えたうえの(@uenoyou111)です( ˘ω˘)
運動は良いと色々言われていますが、体の基本的な機能が向上するのはよくわかると思います。
そして脳にもいい影響を及ぼし、精神的にも多大なる恩恵をもたらすのは今日では当たり前みたいな情報。
しかし、改めて心理学的な研究と結びつけがあるニュースを見て自分なりにまとめようと思った次第です。
ビッグファイブとは
まずここから書き出さねばまとまりません。
ビッグファイブとは、ゴールドバーグ,L.R.が提唱したパーソナリティの特性論で、人間が持つさまざまな性格は5つの要素の組み合わせで構成されるとするものです。「特性5因子論」とも呼ばれます。
人間の性格は、いくつかの要素で学術的に分析する事が可能となります。
その要素は以下の5つとなります。
【外向性】:人とのコミュニケーションに対する積極性
【共感性】:他者とのやり取りにおける傷つきやすさ、気持ちの安定性など
【開放性】:どれほど新しいことに対しオープンになれるか、想像力の程度など
【誠実性】:周囲の人や、物事に対する責任感や計画性がどの程度か
【調和性】:周囲に同調する・従うといった行動ができるか
色々な研究から、文化や民族をも越えた普遍性を持つとされている指標と言われています。
それだけ信頼性のある指標を元に、今回は運動によってどれくらい変動するのか?という部分がキモになるかと思います。
ビッグファイブを簡単に診断できるツールもあります。
意気揚々とIBMのワトソンくんに性格診断してもらっ…あれ? - うえのブログ
人工知能で性格診断してくれるものです。私の場合は紹介してくれた方と同じになってしまいましたが。
運動不足が引き起こす低下要素
まず、この研究が行われる前から運動不足の人は4~10年後に性格的な特性が低下する傾向にあると言われてきました。
更に深掘りして、仏モンペリエ大学・心理学者のYannick Stephan氏が1990年代に運動習慣・健康状態や性格アンケートを約9000人超の被験者から取っています。
そして20年後に再度同じ質問やアンケートをしてみたところ、ビッグファイブの「外向性・開放性・誠実性・調和性」が運動不足により低下が平均して大きく見られたという結果です。
5つのうちの4つが平均して低下しているとなれば、もうほとんど全て下がってしまってると見てもいいぐらいです。
しかし単純な高低では表せられない
下がったからと言って、その結果が全て悪いとは言えません。
株式会社ダイレクトコミュニケーション(https://www.direct-commu.com/company/)によると、ビッグファイブを元に性格診断を行う時。
特性に応じてどこが高いか低いかを伝え、その傾向によるコミュニケーションの注意点を伝えるとのこと。
しかしながらそのばらつきは個人差が大きく、そのグラフの流れ自体が個性となります。
なので一概にここが低いからと言って悪い、とは断定できない部分でもあります。
予防しておくに越したことはない
どの程度変化があるかとかその傾向は個人差が大きく、かと言って低いから悪いとまでは言えない。
けど、グラフが平均的に下がるというのは自分の特性が今とは逆側の影響を受けてしまうという意味でもあります。
狙ってそうなるのであれば問題ありませんが、知らないうちに影響を受けて苦しむぐらいであれば運動を取り入れて予防しておくのが効果的。
家事。すごい運動量を秘めています。
定期的に運動する習慣がつけられなければ、家事は運動と考えを変えてみると良いかもしれません。
まとめ
ビッグファイブのうちどの特性が相互に作用し合うか、とか。そういう部分では追求していない為に少しぼんやりとした内容となっています。
が、運動は様々な面でメリットが大きく、その効果も証明されてきている…というところでしょうか。
そういえば運動の効果を体感しようと、かなり前にふざけた記事を書いてました( ˘ω˘)
適度なのが何事も一番ということです。
ではでは(`・ω・´)ゞ

